第453回 『連チャン症候群』 〜 『役割意識と使命感の自覚』 〜
- 樋野 興夫先生

- 3 分前
- 読了時間: 2分
2025年10月16日 新渡戸稲造記念センターに赴いた。 2025年11月3日(月・文化の日)の【第22回南原繁シンポジウム『敗戦後80年、戦後日本の歴史を見つめ直す』】のチラシが届いた(添付)。 筆者と新渡戸稲造(1862-1933)と南原繁(1889-1974)の繋がりを復習する日となった。
筆者は、島根県の出雲大社の母校の鵜鷺小学校の卒業式で、来賓が話された『ボーイズ・ビー・アンビシャス』(boys be ambitious)(1877年札幌農学校のクラーク博士の言葉)が胸に染み入り、希望が灯るような思いを受けた。 筆者の人生の起点である。 札幌農学校におけるクラーク精神が、内村鑑三(1861-1930)と新渡戸稲造へと導かれ、英文で書かれた『代表的日本人』(内村鑑三)と『武士道』(新渡戸稲造)は、筆者の『座右の書』となった。そして、2人の弟子である南原繁と矢内原忠雄(1893-1961)へと繋がった。 まさにパウロの言葉『すべてのことを働かせて益としてくださることを、私たちは知っています』(ローマ人への手紙8章28節)の実感する日々である。
筆者は、南原繁に会ったことはないが、南原繁が東大総長時代の法学部と医学部の学生であった2人の恩師から、南原繁の風貌、人となりを直接うかがうことが出来た。『高度な専門知識と幅広い教養』&『視野狭窄にならず、複眼の思考を持ち、教養を深め、時代を読む』であった。 【人間は、自分では『希望のない状況』であると思ったとしても、『人生の方からは期待されている存在であると 深い学びの時が与えられ、その時、その人らしいものが発動してくるのであろう。』が『役割意識と使命感の自覚』となろう。】の学びである。
10月18日(土)午前中 東久留米市立第2小学校での『がん教育』の授業を依頼された。【『考え深げな黙想と真摯な魂と風貌こそ、現代に求められる『教育の心得』】ではなかろうか! 10月18日の午後は【がん哲学外来『市ヶ谷だいじょうぶ!カフェ』(代表者:田口謙治氏 担当者:田口桂子氏)(東京ゴスペルハウス内に於いて)】での講演に赴く(添付)。 『2連チャン症候群』の10月18日である。





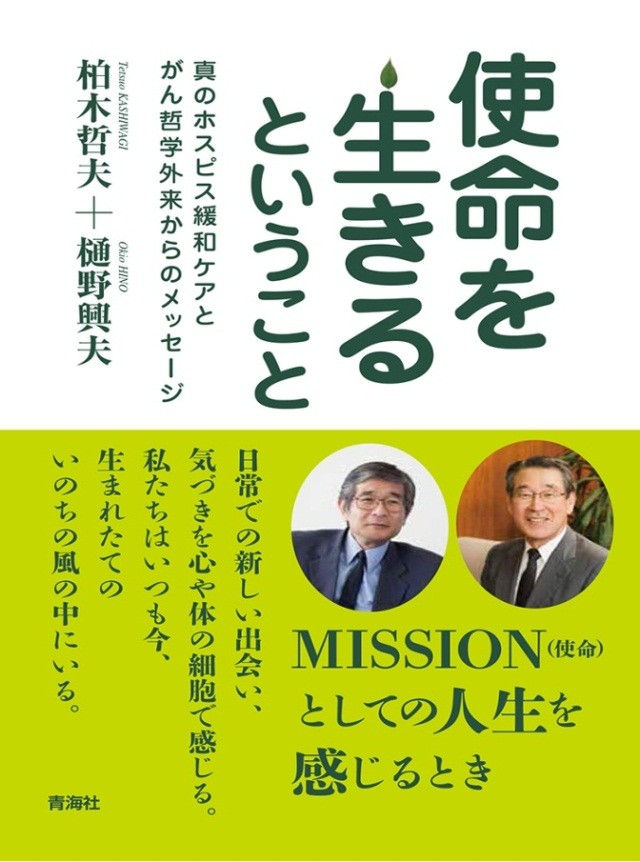

コメント